請求書のデジタル化の準備はお済みですか?e-invoicing が義務化されます
デジタル化
1/31/20241 分読む

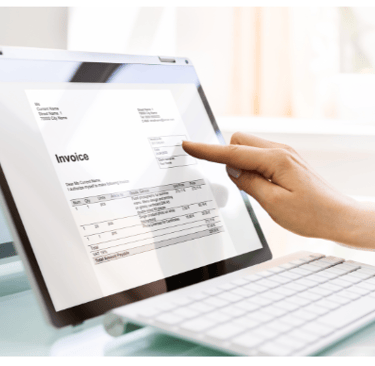
フランスでは2020年より公的機関あてに発行する請求書は電子請求書のみが受け付けられています。例えば市役所などに請求書を発行したことのある方は、紙フォーマットの請求書を受け付けてもらえず指定のプラットフォーム(Chorus Pro)経由で電子請求書を送付した経験があるのではないでしょうか。
公的機関とのやり取りのみであったこの請求書のデジタル化(e-invoicing)が、まもなくフランスでTVA課税事業をおこなうすべての企業に義務付けられます。「知らなかった!」とならないように、いつ、どう変わるのか、以下詳しく見ていきましょう。
e-invoicingとは?
e-invoicingとは請求書の電子化。このシステムが施行されると、対象企業は請求書をデジタルフォーマットで受領、また、発行することが義務づけられます。デジタルフォーマットならなんでもいいわけでもなく、いくつか条件があります。
規準の電子フォーマットにかなっていること
紙の文書をスキャンしたものはもちろん、通常のPDFファイルや行政の認定を受けていない会計ソフトなどで作成した請求書も規準外になります。e-invoicingでは求められる形式は以下3タイプで、XML CII、 XML UBL、それからFacture-XというPDFの中にXML構造を取り込んだ(PDF/A)ハイブリッド式のフォーマットです。請求書発行ソフト各社もe-invoicingの条件を満たした請求書が作成できるように製品アップデートをするとは思いますが、念のため、お使いの請求書発行ソフトではどんな形式のファイルで請求書の発行ができるか、調べておくことをおすすめします。
請求書の記載必須事項が規準の書式をみたしていること
デジタル化しても請求書はこれまでの記載必須事項を引き継ぎます。この機会にあなたの発行する請求書に必要な情報がすべてそろっているか今一度確認してみましょう。これまでの記載事項に加え、デジタル請求書には記載されるべき項目が4つ増えました。
o 発行者のSIREN番号
o 商品の配達先住所(クライアント住所と違う場合のみ)
o 業務の種類 : 物品売買、役務提供、あるいはその両方
o サービス提供事業者がTVA納税時期を売り上げ後のオプションにしている場合その旨明記
そして、e-invoicingの導入で次が一番大きな変更点かもしれませんが、
指定のプラットフォームで送受信されること
紙の請求書を郵送するということは勿論できなくなりますが、デジタルの請求書であっても、取引会社間で直接メールで送受信することもできなくなります。プラットフォームで送受信というのは、請求書を発行する会社がプラットフォームあてに請求書を送信し、受け取り側の会社がプラットフォームに領収書を取りに行く、ということです。中継地点ができるわけですね。どこのプラットフォームを使用するかは各社の自由で、行政機関が運営するChorus Proと、政府の認定を受けた民間会社が運営するPDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire)と呼ばれるプラットフォームの中から選択します。
対象企業
e-invoicing義務の対象となるのは、フランスでB2B事業を行い、TVAの課税対象となっているすべての企業です。大企業、中小企業だけでなく、micro-entrepreneur (旧auto-entrepreneur)も含まれます。
注意していただきたいのはmicro-entrepreneurの皆さんです。「いつも« TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI »と書いて請求書を発行してる私には関係ないな。」と考えたかもしれません。売り上げ基準でTVAが納税義務が一定期間免除されていてもそれはあくまでも免除に過ぎず、TVAの課税対象から外れているわけではありません。みなさんの行うビジネスがTVAの課税対象事業である限りe-invoicingの義務の範疇となります。e-invoicingで発行する請求書にも引き続き« TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI »と記載してくださいね。
TVA非課税事業をおこなう企業やアソシエーション(医療、教育、不動産分野など)はe-invoicing義務の対象にはなりません。また、個人消費者を顧客とするB2Cビジネスを行う企業もe-invoicing義務の対象とはなりません。これらのe-invoicing義務から外れた企業は、e-reportingというこちらも新たに導入されるシステムの対象となります。e-reportingに関してはまた別項でとりあげますので、レストランや小売店などを経営する方はそちらを参考にしてください。
e-invoicingの義務化はいつから?
準備が必要なこの新システム。義務化のタイミングは会社の規模によって異なります。また、発行に関してと受領に関しても、違う日程が予定されています。ご自身の会社でいつから新システムでの請求書の送受信が義務化されるのかしっかり確認していきましょう。また、もともとは2024年の7月の施行が予定されていましたが延期され、2024年度の金融法により新日程が発表されました。
発行
o 大企業及び中規模企業(grandes entreprises と ETI): 2026年9月1日
o 中小企業及びマイクロ企業(PME と les micro-entreprises): 2027年9月1日
受領
o すべての企業で : 2026年9月1日
大企業が2026年9月から新システムで請求書を発行する以上、そのときには受領体制は会社の規模にかかわらずすべての企業でできている必要があります。そうでないと、例えば電気料金の請求書や電話・通信費に関する請求書が受け取れませんからね。
企業分類
Micro-entreprise: 社員数が10人以下でかつ、年間総売上高が200万ユーロ以下あるいは貸借対照表の総額が200万ユーロを超えない企業
PME: 社員数が250人以下でかつ、年間総売上高が5000万ユーロ以下あるいは貸借対照表の総額が4300万ユーロを超えない企業
ETI, Entreprise de taille intermédiaire: 社員数が5000人以下でかつ、年間総売上高が15億ユーロ以下あるいは貸借対照表の総額が20億ユーロを超えない企業
Grande entreprise: 社員数が5000人以上でかつ、年間総売上高が15億ユーロ以上あるいは貸借対照表の総額が20億ユーロ以上の企業
義務を守らない場合の罰則は?
請求書を規準にあったデジタルフォーマットで発行しなかった場合は、ルール違反の請求書一枚につき15ユーロの罰金が科せられます(ただし年間の上限15000ユーロ)。
e-invoicing導入のねらいは?
そもそもなぜe-invoicingシステムが導入されるのでしょう?フランス政府のねらいは以下のように説明されています。
TVAに関する不正をふせぐ
デジタル化によって支払いサイトの短縮や事務処理の軽減が見込まれ、企業の競争力を高めることができる
事前自動記入によってゆくゆくはTVA申告の簡易化をめざす
企業の活動動向をリアルタイムで認識できる
おわりに
会社の規模や構造によって新システムへの対応準備はかわってくるかと思います。それぞれの組織にあった方法を今からしっかり準備したいですね。
--------------------------------------------------------------------------------------
参考になるサイト
https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A15683
--------------------------------------------------------------------------------------
当記事への感想や質問、ほかにも扱ってほしいテーマなどありましたらメールでどうぞ!
Adresse
144 rue Paul Bellamy, CS 12417
44024 Nantes Cedex 1
Contact
contact@sayacc.com
07.44.40.03.52
EI YAMAGUCHI SOULARD Sachi
n° SIRET 453 783 342 00026
